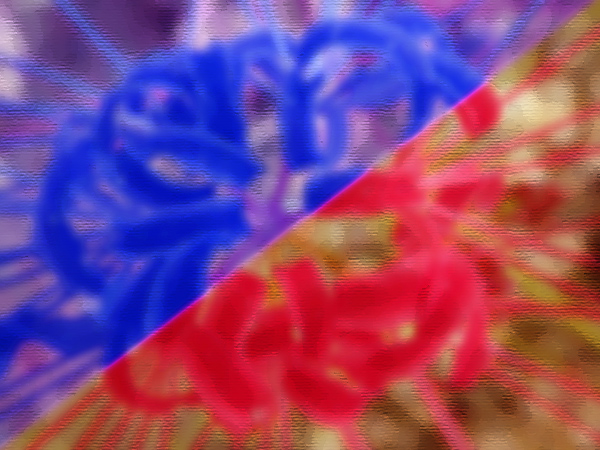白驟雨が視界を遮る、遅い夕刻のぬかるみを歩くマイクロトフは、濡れた服の中で身を震わせた。
嘗てこうした雨の中を征くとき、大抵は、蹄に蹄鉄を打った馬の高い背に揺られ、時には着込んだ鎧の隙間から染み通る、湿り気と金属の臭いに包まれて道を進んだものだった。
鈍い銀色の毛並みに包まれた体躯を巧みに操って、彼に忠実に歩き、駈けてくれた、芦毛のズィルバーンを恋しく思う。数年間彼と戦場を共にした馬は老いて駿馬とは云えず、彼は名残を惜しみつつ、旅に出るとき、彼女をノースウィンドゥの厩に預けてきた。
それに、これからひたすらに急峻な山道と街道を縫ってゆく旅に、騎馬であることは、もはや身軽であるとは言えなかった。
別れを告げた朝、厩舎の戸口から振り返ったとき、ズィルバーンが自分を慕わしげに見つめる、澄んだ青い瞳を、別れから一年経っても彼は忘れられない。
ぐっしょりと濡れて重みを増した荷を担ぎ直し、男は、雨を避ける役目を果たすことの出来なくなったフードを指先で押し上げた。濡れて張り付く、柔らかな黒髪ごしに、今宵の宿の目印である灯りを見上げる。それは紅色の火屋にくるまれて、降りしきる雨の中に不思議な光の円をえがいている。宿の名は、烈火、柘榴石、を意味する「パイロープ」という。
その宿は男が選んだものでなく、そこで日を決めて落ち合う筈の相手が、ひとつきぶりの約束の場所として定めた、旅人たちの間で名の知れた宿であった。
早い夕刻。
自分の身体から泥の汚れや汗を洗い流す湯の、甘い柑橘の香りを、マイクロトフは若干擽ったいような気分で嗅いだ。彼が宿に着いたとき、外は刃が降り注ぐような雨の降り始めだった。短時間雨に濡れただけで濡れそぼって着いた彼を、宿屋「パイロープ」の主人は、湯浴みの用意が出来ていると云って出迎えた。
ひと月前にここに立ち寄って、滞在の日取りを決めた際、殊に自分たちの為の湯あみの支度を頼みはしなかったため、マイクロトフは戸惑ったが、同日夕刻に到着する筈だった、トランの貴婦人の一団が、雨のためにまだ着いていないことを主人は話して聞かせた。
蜜で溶いた高価な石鹸も、岩場の浴場を満たした湯も、一晩とっておけるものではない。
マイクロトフは主人の好意に甘えて、貴婦人たちの入浴の為にしつらえた支度そのままの浴場で汗を流した。甘い香りの石鹸で体や髪を洗っていると、岩をくり抜いた浴場の窓から、昏い雨のしぶきが見える。マイクロトフの待ち人は今夜のうちにたどり着くだろうか。彼はいまだあたたまらない体を、オレンジの花の香のする湯に沈めて目を閉じた。
この甘い香りは自分ではなく、宿にこの後やってくる筈の友人に似合うと思った。
少年時代に親しい友となってから、マイクロトフとカミューは常に共にいられた訳ではない。そもそも見習い騎士から正騎士となったおり、彼らは勢力争いの絶えない、別々の騎士団に叙任されることとなった。
少年から青年に成長するに従って、彼らはお互いをかけがえのない相手だと自覚したが、時計の針が時を刻みながら遠ざかり、また近づいて一つに重なるように、遠く、近く、逢瀬を重ねるしかない期間が久しく続いた。
その期間が長ければ長いほど、マイクロトフの中でカミューへの想いは強くなった。遠征や国境の警備に携わる若い兵士だった頃、まだそれが恋だと自覚する前から、触れることのできないカミューの肌や髪、見つめる目、声に焦がれ、自分が恋しさから彼を美しく描きすぎているのかとさえ疑い―――、そして、再会の度にカミューの全てが自分の記憶を塗り替えることに驚かされた。
ロックアックスに据えられた、騎士団の主の城に、騎士団の長同士として住み、頻々と顔を合わせることができるようになったのは、初めて出会ってから十年のちのことだった。
そうして時を過ごすうちに、カミューと離れ、のちに相まみえる日を待つことは、マイクロトフにとって特別なことになっていった。
マイクロトフは、音楽に深く親しむ方ではないが、彼はカミューを待つとき、得がたい音楽の始まりを待っているようだ、と心のなかで明らかにした。
他の者との関係には決して介入しない、甘いときめきや期待を孕んで、こころの中に流れる曲。
選び抜かれたなめらかな楽器が並び、それぞれの音色が念入りに調律される。曲が始まるまでの調律の音の流れにさえ、とろりとひたりこむ観客のように、マイクロトフは彼との再会を待っていた。
雨の中をこの宿にへ向かうカミューが、離れていたひとつきの間に、何者かに害されたり、彼とおちあう気持を変えるとは思えなかった。
カミューの強さを信じていたし、彼の気持ちを信じていた。
マイクロトフが、雨の音を聞きながら数刻待ったとき、宿の主人がマイクロトフの部屋の戸を叩いた。
「お連れ様がお見えですよ」
広い部屋を数日借り上げたマイクロトフが、宿を共にする相手を待ちかねていたことを知る主人は、丸顔に気立ての良さそうな笑顔で、新たな客人を招き入れた。
宿の主人の後ろに立つ、主人よりだいぶ背の高い細身の男を見たとき、マイクロトフは、挨拶よりも一瞬の驚きで声を飲み込んだ。男の皮膚は、カラヤ族のような完璧な小麦色であり、マントの下で額や頬に濡れてまつわる髪の色は、黒に近い褐色だったからだ。
主人は、厚いタオルを一抱え、新来の男に手渡し、采配をする為に下へ降りていった。
「たった一月逢わないでいるうちに、随分面変わりしたようだが」
ほっと息を吐き出してマイクロトフが言うと、染めたらしい髪から落ちてくるしずくを拭いながら、それだけは色の変わらない、バルト琥珀のような翠色の目を和ませてカミューは微笑った。
「ひどく腹が減っているんだが、まずはこの、面変わりの種を洗い流したいものだな」
「一体何故そんななりをしている?」
音楽のようなカミュー。音楽のような声。マイクロトフはそれを味わいながら、自分の変えようもないならわしとなった、堅く低い声で尋ねた。
彼は首を振った。
「話せば長い」
そう云った彼の方では、湯浴みを済ませて、乾いた服に着替えたマイクロトフに目を止めたようだった。
「御前は随分さっぱりしているようだが」
「夕方までにパイロープにたどり着けなかった、ご婦人方の湯浴みの支度を譲って貰ったんだ。まだ湯を足してもらえるだろう。お前も相伴に預かってくればいい」
カミューは微笑した。彼が目を細めて笑うと、部屋の灯りを受けてうるんだように輝きを帯びる。
「そうしよう。それから夕食と酒だな。わたしの舌は、ここへ来るまでにすっかり凍ってしまったよ」
風呂で体を温めて帰って来たカミューの髪が、豊かな光沢と濃淡をふんだんに持った紅赤に、皮膚は淡く金色に焼けた白に戻っているのを見てマイクロトフは、ようやく見慣れた相手と向かい合った思いで安堵した。部屋の隅々に、贅沢に灯された洋灯が、夜の室内を暗い金色に染めており、柔らかな癖のあるカミューの髪は、まさに光をあてた、熟れた石榴のように輝いていた。
荷がすっかり濡れたため、宿に借りた、簡素な麻の服を身につけて寝床に足を投げ出したカミューは、そんな格好をしていても、赤と緑の宝石をはめ込んで細微に彫った、象牙の細工のようだった。しかし彼は細工物とは違って、体中がきわめてしなやかな線で構成されており、湯殿で温めた皮膚や髪は、花と蜜の香りを漂わせている。マイクロトフと同じように宿にやってきて、同じように香りと安息のもてなしを受けたカミューは、だがマイクロトフとは何か違ったゆるやかさ、目に心地よいけだるさ、体の内側からにじみ出すような不可思議な光をまとってくつろいでいた。
「姿をくらませていた間の話をできるほどには、凍った体は溶けたか?」
呆れた口調でマイクロトフが云う。これは半ば自虐の言葉でもあった。
逆の立場なら、こんな風に相手の居所が分からなくなることなどないだろうに。カミューは、離れている相手の居場所を、ふいとたぐり寄せるような、個人の手づるを幾つも持っていた。
「この一月、実はティントに居た」
「ティントに?」
訝しむマイクロトフを軽く手で制して、カミューは、聖水のように戴いた硝子のグラスの葡萄酒をぐっと深く一口飲んだ。酒が喉を通ったのだろう。は、と満たされたため息をつく。
カミューは、意識を濁らせるほど飲むことは殆どなかったが、純粋に酒は好きだ。陽気な好い酒で、冷える晩には辛口の赤葡萄酒を、夏にはよく冷やした蒸留酒を好み、飲めばよく笑い、語り、触れ合うことにもより積極的になった。
「ティントでジーン殿が紋章の学び舎を作る計画をしておられるだろう?」
マイクロトフは頷いた。それは風の噂に伝わって来ていた。
ティントは真の紋章を持つ者と縁が深い。それに加えて広大な森を有した、移民を受け入れることのできる土地柄である。今までそれをしなかったのは、ティントの閉鎖的な体質によるものだった。
長らくグリンヒルに紋章師の拠点を据えていた美しい魔女たちは、法を整備し、魔力や戦術と徐々に手を切りながら、近代的な街に復興してゆこうとする、新市長テレーズの、新生グリンヒルに馴染まなくなりつつあったようだ。周辺の国々は驚いたが、その紋章師たちをティントが受け入れた。変わろうとしている街は、一つ、二つではない。
「お前も知っていることだが、ルルノイエ攻略で城主殿と戦いの一部始終を共にして、わたしの魔力は著しく上がった。自分で制御するのが困難なほど」
マイクロトフは頷いた。
ルルノイエ攻めの後、カミューの烈火は幾度となく暴走した。真の紋章の眷属とはいえその力は大きく、潜在するその力が魔力の上昇と相まって、カミューは初めての紋章酔いの頭痛に苦しみ、度々隠れて吐いている姿を見ることもあった。
いっときはジーンに、封印の護符を埋め込まれたこともあった。
烈火を封じる護符を、てのひら側から術で埋め込まれたカミューは、どれほどの苦痛を味わったのか、苦しげな喘鳴の中で、二度ほど叫び声を上げて、術を行う寝台の横に立ち会ったマイクロトフをぎょっとさせた。カミューは今までどんな時も、そんな風に絶えきれない苦痛の悲鳴を上げることはなかったからだ。
封印の術を受けるカミューの声をかけてよいものか迷いながら、術が行われているのとは逆の手を握りしめると、カミューは汗に濡れた前髪の中で堅く閉じていた目を、かすかに開いた。ところどころ、その体の主人によって噛み破られ、乾いた唇がマイクロトフ、と呼びかける形に動く。
その直後、痛みの熱に火照った頬の上に、汗とまじってすうと流れた落ちた一条の涙は、不謹慎なようだが、マイクロトフの心臓に衝撃を与えるような美しさだった。
あの声にならない呼びかけの声。
マイクロトフを見つめる目。
そもそも友人として既にカミューは最愛の男だった。既に彼の全てを肯定していた。
だが、他の者には聞こえないように呼ばれた名前と、果実を滑り落ちるようなあの涙が、マイクロトフを他ならない深い恋情に落とし込んだきっかけとなったように思う。
マイクロトフは、カミューが復調してすぐに、己の気持を打ち明けた。
カミューからどんな答えが返ってくるのか想像がつかなかったが、隠してはおけないと思った。
それでもひそかに恐れずにはいられなかった、嫌悪や戸惑いをカミューは見せず、首を少しかしげるようにした。数度瞬きし、更に考え混むような表情を見せた。
「……どうやらお前に先を越されたようだ。他ならないお前のことだからおろそかにはできずに……、わたしも自分の気持に何と名付ければいいのか迷っていた。だが、お前のおかげで迷う時間を空費せずに済んだようだ」
微笑する。
「礼を云うよ」
そうして、彼らの立っているノースウィンドゥの庭の周辺に人が居ないことを確かめるように、ちら、と目を走らせたあと、マイクロトフの首筋を軽く引き寄せて、低く、真摯な声で囁いた。
「お前も無二の存在だ」
そして、敢えて瓦解した騎士団の名を冠して付け加えた。
「わたしの青騎士」
歌うようにゆるやかな声で。
そして彼らの間柄には、友人同士だった時の親しさに加え、口づけや抱擁や、時折蜜に漬けたような甘い言葉が加わった。そのほとんどはカミューが口にしたものだが、これについては、マイクロトフはカミューに新しい快楽を独占させなかった。カミューを賛美し、思いを伝えることで、彼を狼狽させる希な瞬間を愉しんだ。それらの新しい要素は彼らの邪魔にはならず、互いの側にいることを余計に居心地のよいものにし、距離が離れれば再会を望む苦しみを帯びた甘い香料となった。
それから一年ほども経ち、二人がデュナンを出発する秋が訪れた。
「烈火の扱いに困ることはほとんど無くなったが、まだ自分の魔力に伸びそうな気配があってな」
カミューは、そこに魔力の泉があるように、そっと右手の甲を撫でた。
「剣士から紋章師へうつることの道について、ジーン殿や、他の著名な紋章使いの方々に話を聞いてきたんだ。いくつか、新しい紋章を宿すこともしてきた」
カミューは物思いにふけるようにふっと目を伏せた。
「ティントは今だいぶ国境を開いていて、以前とは往来する者の数も、性質も変わってしまっていたよ。宿屋にも、紋章師の集まりにも人が多く集まる。デュナン統一戦争でわたしは顔を売りすぎてしまったので、肌や髪の色を変えた方がいいと、ジーン殿に云われたんだ」
「それで……」
マイクロトフは納得してうなずいた。
「この一月は、舞台役者の使う化粧の練り粉でカラヤ風の肌で歩き回っていた。なかなかさまになっていただろう?」
話すときほんの少し語尾を上げる、カミュー独特の声が笑いを帯びている。
「似合う似合わないより、お前が見知らぬ格好で現れるのは心臓に悪い」
マイクロトフは文句を云った。
「ティントの紋章師の方々に逢いに行くなら、おれも連れてゆくか、せめてそう云ってから出発てばいいものを、一月も音沙汰無しに放っておくとは」
マイクロトフの抗議に、カミューは詫びるように、数度うなずいてみせた。
「お前はデュナンで死んだ騎士たちの形見を、彼らの故郷に届けることを旅の目的にしていて、目前の悩みがなかっただろう?」
慎重な口調で続ける。
「わたしには、お前の行く道はいつも明るく見えてしまう。自分の心が何を考えているかなど構わず、放棄して、お前に引きつけられるままに後を追っててしまう。だからほんの少しの間、お前から離れてみることを考えた」
カミューの言葉に心底驚かされたマイクロトフは、もたれかかっていた壁から、思わず椅子に座り込んだ。すぐには言葉を見つけられずに、寝台の上に座って低く語るカミューの、おだやかに座る姿を見つめた。
「……ひと月で結論は出たのか?」
「そうだな……」
カミューは、いまだ微笑を含んだ声で言葉を続けた。
「魔術や紋章について学ぶことをやめることはないが、結局お前なしで何かをきわめようと、毎日がつまらないことが分かった」
マイクロトフを見つめる目が優しくなごむ。
「旅のゆくゆく道で魔術を学びながら、魔術の赤の力と青の力から、紫のアカサにたどり着くのを模索して―――そのさなかにも剣を帯びて、お前と、街道から街道を旅することが、わたしにとって一番よい日々であるだろうと、そう考えるに至ったようだ」
カミューの言葉に胸を打たれながら、マイクロトフもまた、外すことのできない騎士の紋章について考えている。剣と紋章の世界。それらはほぼ戦いの象徴であり、ほんの一部を除けば他者を害する道具として洗練されたものだ。
彼らは二人ともが久しく、剣と紋章と共に過ごし、いまもなおそれらに縛られている。剣も紋章も今は彼らの生きてゆく道の切り札にはなりえない。しかし手放すことは出来なかった。カミューとマイクロトフが、どうやら互いにそうであるように。
「お前に会ったらそんな話をしようと、わたしは雨の中をパイロープへ向かいながら考えていたよ。お前は秋に入ってどう過ごしていた?」
「おれはお前と先月別れたあとも、復興を引き継ぐ者を選ぶのにあちこちと尋ね歩いていた。ノースウィンドゥ城では城壁の塗り直しをしていたので、この腕で加わっても来た。体を動かしていれば余り思い悩まないからな」
ちくりと皮肉の棘を含ませたつもりだったが、カミューは平然と耳を傾けている。
「トラン湖の近くで山賊狩りの一員にも加わって、久々に稽古以外で剣をふるった」
「村の自警団に迎え討たれると思っていたのに、あんな大ぶりの両手剣を持った大男に叩きのめされたのでは、山賊も散々だったことだろうな」
大男とは何だ、と思いながらも、マイクロトフは反論しなかった
「お前らしい時間の過ごし方だったな、マイクロトフ」
「そうか?」
こんな風に不安と期待にせき立てられるように、駆け巡ってはたらいていたこのひと月は、自分らしかっただろうか?しかし、そのことを頭から振り払って、伝えたかった言葉の続きに移った。
「その合間合間には、いつ今度カミューに会えるのかとばかり考えていた。さっきパイロープにたどり着いたお前の顔を見るまで、本当にそればかりを考えていた」
洋灯の金色の光に染まったカミューの頬にかすかに朱が走ったように見えた。
「むしろ、お前を想う合間に日々を過ごしていたという方が率直かもしれない」
マイクロトフが畳みかけるとカミューはふ、と低く笑い、次いで声を立てて笑った。
「何ということだろうな、元マチルダ騎士団、青騎士マイクロトフ。そしてわたしも、本当に困ったことだ。わたしたちは互いに何と他をなおざりにして、お互いを慈しみあっているのだろうな」
マイクロトフは慣れない物言いをして乾いた唇を湿そうと、パイロープの主人の煎れてくれた、すっかり冷めた香草の茶を一口飲んだ。
「他をなおざりにしているわけじゃない。ただお前が特別というだけだ」
彼は少し考え、少なくともおれは、と付け加えた。
香草茶の二口目を飲もうとした時、カミューが彼がカップを持つ手を軽く押さえ、唇を合わせた。彼の巧みで柔らかな舌と共に、甘酸っぱいものがとろりと流れ込んで来る。一瞬カミューの舌に歯を立てそうになったが、彼はその甘いものを巻き取ってカミューから受け取って無事に飲み下した。喉の奥へ酸味が通り過ぎてゆく。離したカミューの唇が薄赤く濡れて見える。
「石榴の蜂蜜漬けだよ、ティントで頂いたものだ」
カミューはささやいた。
「魔術とは関わりがないが、これもまた等しく天地からの恵みだな。蜜に浸かったものは病や腐敗を遠ざけるそうだ」
睦言の語尾をさらうようにカミューのうなじを引き寄せて口づけると、カミューは座ったままのマイクロトフを身を投げ出すように甘く抱擁した。同じ湯で清め、温めてもかすかに違う香り、違う温度の体が、ゆるやかな波のように被さってくる。
「こんな風に自分の道を自由に選び、好きな場所に歩いてゆくことが出来て、しかもお前と共にそうすることが赦される。まるで夢のようだ、マイクロトフ」
マイクロトフはうなずいた。待つのもいい。だが、共に居られることについてはカミューとまったく同じ気持ちだった。夢のようだ、という甘い言葉にも共鳴した。
「カミュー、抱いていいか」
自分の言葉を彼に添って返す代わりに、マイクロトフは自分の背に巻かれていた腕をほどいて立ち上がり、カミューを寝台の方へと一歩引きよせた。
「疲れていないか?」
そろりと尋ねると、カミューは後ろの寝台へと更に一歩引いた。
「どんな時でも、隙さえあるならお前に抱かれたい」
低く答えた声は、かすかな欲情のかすれをおびていた。
この部屋の扉を開けるまで、肩書を捨ててそれぞれ一人で歩く旅人だった二人は、再び一対になった。そのつながりに名をどうつければいいのかは互いに分からない。
ただ一対であるとしか。
マイクロトフが落ち合う宿に「パイロープ(石榴石)」を推したため、カミューが敢えて携えてきた、小瓶に入った蜜漬けの石榴。冷めた茶。飲みかけた葡萄酒。それらは全て小さな木彫りの机に置き去られ、暗転した幕の小道具になった。
舞台は寝台へと移り、その後は雨と混じって、待ち望んでいた演奏が始まった。
了